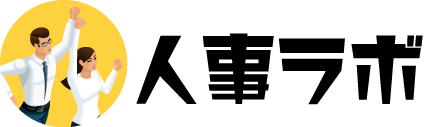心理学をビジネスに活かそう!(3)モチベーションの2つの源泉
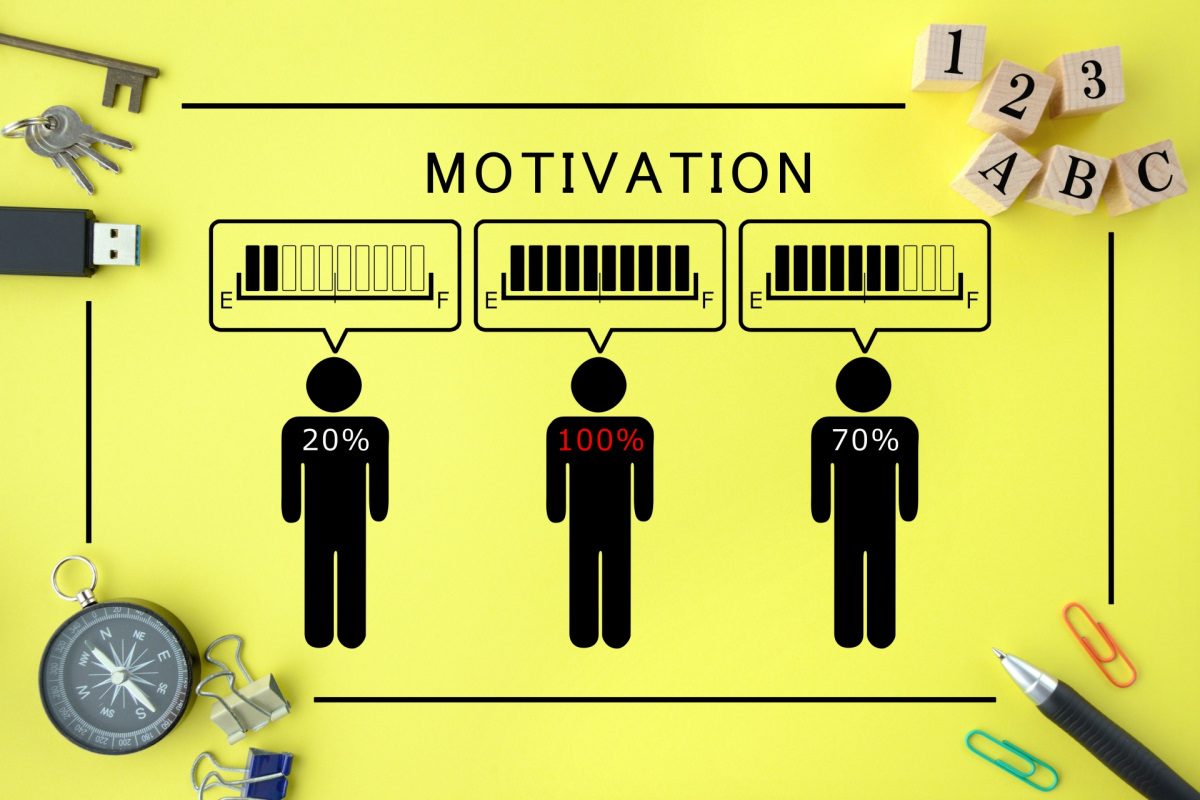
モチベーション(動機づけ)には大きく分けて2つの源があります。
それは、外発的な要因と内発的な要因です。
■外発的モチベーション
人は嫌な仕事でも、お金を稼ぐために働いたり、上司に怒られるのを避けるためにしぶしぶ頑張ってやることもありますよね。このように、外的要因(他者からの賞賛・叱責、報酬や罰など)によって引き出されるやる気のことを「外発的モチベーション」と呼んでいます。
この外発的モチベーションには、さらに次の2つに分けることができます。
●報酬
金銭、賞品、昇格・昇給など、物理的に獲得できるご褒美と、褒められる、表彰される、お礼を言われるなど、心理的な喜びになるものがあります。
●罰
減俸、降格、降給、罰金など、物理的に受ける罰と、叱られる、軽蔑されるなどの心理的な罰があります。
●報酬と罰による動機づけ実験(ハーロック)
アメリカの発達心理学者エリザベス・B・ハーロック(Elizabeth B. Hurlock)は1925年に次のような実験結果を報告しました。
子供たちに数回試験を受けさせ、そのたびに、3つのグループに分けて、モチベーションがどう向上するかを調べたのです。
・褒め続けるグループ
・叱り続けるグループ
・何もしない(放任)グループ
叱り続けるグループの子供たちは、叱られた直後は期待に応えなければと頑張るものの、その後は叱られる毎にモチベーションは低下していきます。
それに対して、褒められ続けるグループは、褒められる毎に、モチベーションが向上し、連動して成績も向上していきました。
●罰の効果は限定的。報酬を含む外発的モチベーションは、持続力に欠ける。
このことから、「罰」は一時的にモチベーションの向上に効果を出すことができるが、それが続くと逆効果だということが分かりました。また「報酬」であっても、それが無くなれば、モチベーションは続かないこともわかりました。
■内発的モチベーション
私たちは、行動を行うことそのものが、その行動の報酬、または目的となることがあります。
例えば、研究者が、ある研究を開始して、調べれば調べるほど面白い現象が見つかることから興味が深まり、どんどん新しい発見をしていく自分に喜びを感じて、その研究に夢中になっていく様子。
このような場合は、報酬や罰といった外発的要因とは別の、自分の内側から生まれてくるものが、その人の行動の誘因になっていると考えられます。
内発的モチベーションの源には、次の3つがあげられます。
●知的好奇心
読書や勉強が嫌いな子供でも、自分の好きなもの、例えば動物について書かれている図鑑や本を読み漁ったりすることがあるでしょう。仕事でも「面白そうだ」と感じることで、その仕事にのめり込んでいく場合も多いものですね。
●自己有能感
人よりも上手にできる感覚を「有能感」と呼びます。最初は苦手な仕事や勉強も、どこかで「コツ」をつかみ、成果を出せるようになっていくことで、面白くなり、自発的に取り組むように動機づけされることがあります。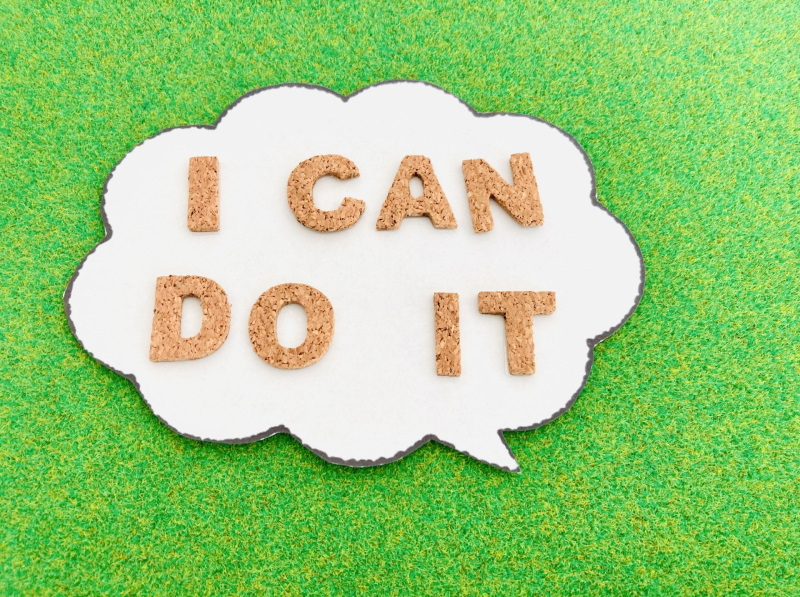
●自己決定
私たちは、他人から指図されたことよりも、自分で決めたことの方が責任感も増し、意欲的に取り組むようになります。
●自発性も、持続性も高い、内発的モチベーション
好奇心や有能感、そして主体的な自己決定から生み出される内発的モチベーションは、その活動や行動を行うこと自体が、目的となり、報酬となります。そのため、罰や報酬の外発的モチベーションによる行動より、自発性や持続性があり、より高成績や創造性を生み出す成果にもつながりやすいと考えられています。
仕事や職場でも、働く人のモチベーションを「信賞必罰」だけで維持しようとすることには限界があります。
「その人の内から湧き出すモチベーションを育むために、どう関わるか?」
部下やチームを持つすべての人に、工夫していきたいものですね。