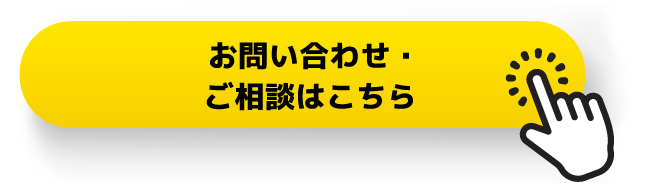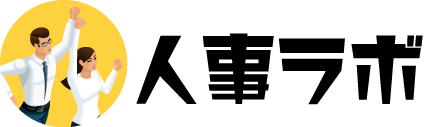採用ミスマッチを防ぐための考え方

「自社分析」を、
採用活動を始める前に行う事が大事です。
人事ラボ編集部のパステル★大嶋です。
「良い人材の応募であったが、自社の欲しい人材と異なるので、泣く泣く不採用にした」
「色々と手を凝らして、ようやく採用出来た人が、入社1週間で退職してしまった」
「経験者/有資格者が欲しいのに、未経験者/無資格者の応募しか来ない」
採用に携わられている皆さまの中には、
こんな経験があるという方も、きっと多いのではないでしょうか。
事実、私がお会いしてきた、困りごとをかかえられている企業様の中には、
・応募(の数/質)が獲得できない
・採用後の定着率が悪い/離職率が高い
といった部分で悩まれている企業様が多い印象があります。
<良く伺う理由ベスト3>
1)応募者が足りず、質の良くない求職者を採用せざるを得なかった
2)選考に進められる人を厳選したが、面接辞退/内定辞退によって採用出来なかった
3)採用をした人員が早期で退職してしまった
母集団形成のために、
とにもかくにも「応募数を取りに行く」戦略を進めていくことは重要ですが、
せっかくの応募も有効な採用に繋がらなければ、意味がありません。
ということで今回は、採用ミスマッチが起こる理由その1、
「応募者が足りず、質の良くない求職者を採用せざるを得なかった」
が起こる理由を細かく分析し、解決策をお伝えできればと思います。
1、採用難度・ハードルの高すぎる人材の募集だった
例えばですが、
「弁護士先生の募集をする」「お医者さんの募集をする」
こんな想像をしてみてください。
「やった事ないけど難しそう」←こんな印象を持ちませんか?
ちなみに、きちんとした理由としては、下記のようにロジカルに答えられます。
「弁護士資格を持っている人材は2020 年3月 31 日現在で
4万 2,164 人(Google調べ)なので、単純に47都道府県で割って
1都道府県当たりで897人だから、そもそもの人数が少ないので、採用が難しい。」
「医師免許を持っている人材の少なさもさることながら、
外科・内科など、専門分野ごとに担当出来る領域が異なることから、
特定のスキルを持つ人材がたまたま採用市場で転職活動中である可能性が
極めて少ないため、採用が難しい。」
上記をシンプルにすると、
「○○の資格を持っている人材は、そもそもの人数が少ないので、難しい。」
「そもそもの母数が少ない中、○○のスキルを持つ人材がたまたま転職活動中
である可能性が極めて少ないので、難しい。」
という事になります。
上記は極端な例なので、実際の募集を行う際には
ここまで採用難度の高いものである事は少ないとは思いますが、
そもそものユーザーが少ない募集の採用難度が高くなりやすいことは自明です。
考えるべき点としては、
・採用ハードルを下げることが出来るか?
・その人材を採用した時に、どんな業務を任せるつもりなのか?
代替できる人材がいるとしたら、どんなターゲットになるのか?
上記のような点を検討すると良いと思います。
2、採用に利用した求人媒体・メディアが適切ではなかった
例えばですが、シニア採用を検討している企業様が、
10代~20代の若者向けのメディアに求人広告をご掲載したとして、
正直に言って、あまり上手く採用が出来るビジョンは浮かばないですよね。
逆もまた然り、若者を採用したい企業様が、新聞の3行広告スペースに求人をご掲載したとして。
新聞の購読数が減っている昨今という事情もあり、こちらも正直に言って、あまり上手く採用が出来るビジョンは浮かばないです。
「いつものメディアに1本電話」で簡単に掲載出来るのは便利なことだと思います。
ですが、どんなメディアにも得意・不得意はございます。
今の募集では、ターゲットの利用頻度の高いメディアを利用するのが鉄則。
ネットメディア/紙メディアという大分類だけではなく、
ネットメディアの中でも、動画メディア/SNS/求人検索エンジン/求人媒体
紙メディアの中でも、ポスティング/新聞チラシ・折込/フリーペーパー
といったような、その時々の使い分けをお勧めいたします。
3、急な欠員募集で採った人材で、精査が十分に出来ていなかった
以前より「事前の調査」が非常に重要だということは
何度もお伝えしてきた内容ですが、
これは市場調査に限った話ではありません。
言ってしまえば、
採用ターゲットの言語化をすることが
出来ないまま走り始めてしまった採用は、
精度の低い活動になってしまう可能性が高いのです。
当社では、「採用ターゲットの言語化」の事を
「採用ペルソナの設計」と呼んでおり、
解決策としておススメの出来る手法となります。
手法を行うのには、
その人に求める「Must」と「Want」を絞り込み、
不必要に採用難度を上げないための話し合いを
ブレストベースで行うのが、
やりやすいのではないかと思います。
例えば採用を上手くできなかった企業様でよくある例ですが、
設計した採用ペルソナを紐解いてみると、
「Want=望ましい条件」を大量に入れており、
「Must=絶対に必要な採用要件」については
資格についてしか触れていなかった
といったことがございます。
採用要件についてきちんと精査していく事で、
求人広告の中身のクオリティをアップさせることもできるので、
絶対に行うべき項目です!
いかがでしたでしょうか。
「応募数が足りなかった」理由を明確にすることで、
次回以降の採用活動で有利に立ち回ることが出来ます。
当社では、貴社専任のコンサルティングが営業担当として、
採用が上手く行かなかった理由の言語化から
改善策のご提案まで含め、貴社採用成功に向けて伴走させて頂きます。
コンサルフィーは無料ですので、お気軽にお問合せフォームよりご相談ください。