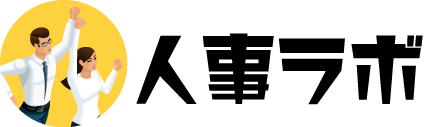(5)楽観的思考「なんとかなる」をつくり出す/社会人に求められるもう一つの能力「感情知能(EQ)」

第4回では「セルフ・エフィカシー(自己効力感=やればできる感)」について紹介いたしましたが、今回は、「楽観的思考」について考えてみたいと思います。たとえ悪い状況でも明るい見通しを持ち、前向きに行動するような人の典型的なセリフがあります。それは「なんとかなるさ」です。
この「なんとかなる」に象徴されるのが「楽観的思考」というわけです。
一見、ネガティブな状況下で、ポジティブな面を見出す思考力ということもできます。
減ってしまったコップの水が、
「もう半分しかない」と捉えるか
「まだ半分もある」と捉えるか
この捉え方(思考)の違いで、私たちの感情や行動が変わってきます。
・明るい見通しを持ちながら物事に取り組む
・失敗や否定的な出来事を潔くあきらめることができる
・気持ちの切り替えが上手
・「なんとかなる」という思いが周囲に伝わりムードメーカーになる
・慎重さに欠ける
・失敗への対策の準備不足
・悲観的な予測をすることで、実行する意義や意味を疑ってしまう
・失敗すると悲観的な予測が的中したと思い込み、さらに悲観的な予測が増える
・「どうせムリ」などのネガティブな発言が伝播し、周囲の士気を下げる
・リスクマネジメントの意識が高い
・準備を怠らない
■ストレス耐性やレジリエンスとの関連も高い
ポジティブ心理学の創設者で、米国心理学会会長でもあったマーティン・セリグマン博士によれば、「楽観的な人は悲観的な人に比べて成功体験を持ちやすく、ストレスに対する耐性度が強い」とのことです。
また、楽観性が強い人は「レジリエンス(回復力)」も強い傾向にあることがわかっています。
■セールスの業績や定着要因にも影響か
セリグマン博士は生命保険のセールス職を対象に、1年目の営業成績を調べた結果、楽観的思考の高いセールス職は、悲観的思考が高いセールス職の29%も販売成績が高く、さらに2年目では130%も高く、2倍以上の成績の差が開いていたそうです。
しかも、2年目も仕事を継続していた人の67%が楽観的思考が高い人々だったのに対して、離職してしまった人の59%は悲観的思考が高い人だったとのこと。
販売成績のみならず、人材の定着にも「楽観的思考」は影響があるようですね。
特にリーダーの楽観性が発揮されると、困難な場面でも「なんとかなるよ」という前向きな言動とともにチームにポジティブな雰囲気を生み出す源になります。
<楽観的思考を高めるために今日からできるトレーニング>
(1)できない理由よりも「できる方法」を考える
悲観的な思考の下では、「できない理由」ばかりを並べ立てて、動けなくなりがちです。
何か一つでも「できる方法はないか?」。ここに焦点を当てて思考してみましょう。
特に、チームでの話し合いでは「できる方法」を話し合うことで、互いの楽観的思考が影響し合い、未来志向のモチベーションが高まっていくでしょう。
(2)白黒思考に気づき、修正する
良い・悪い、0か100か、敵か見方か、成功か失敗か、白か黒か、など二者択一だけで考えてしまっている「白黒思考」「完璧主義」「べき思考」に気づいたら、「例外もある」「第3の道もある」「グレーゾーンもあるよ」と許容範囲を広げて考え直すと、偏った悲観的思考を修正しやすくなります。
(3)失敗の原因を引き受け過ぎない
失敗の原因の切り分けが下手な人は、すべて「自責」として引き受けてしまい、悲観的な思考を自己強化しがちです。 次の3つのパターンで原因の捉え方を変えてみましょう。
・「不注意」のパターン → 反省して注意リストを作成する
・「知識・能力不足」のパターン → 学ぶ機会とする(勉強する、訓練する)
・「不可抗力」のパターン → 潔くあきらめる
(4)「感謝言葉」を使う
ネガティブな言葉が多いと気づいたら、あえて「ありがとう」などの感謝言葉をはじめとするポジティブな言葉を発するようにしてみましょう。悪い状況を受容れつつ、心が落ち着いて、状況を冷静に見直すことができるようになります。
(5)「3 Good things」 を書く
今日の出来事を振り返り、3つの良かったことを書き出すことを日課にしてみましょう。小さくても、良い出来事、恵まれていたこと、ありがたかったことを思い出すことで、楽観的なものごとに目を向ける習慣が身につき、ストレス耐性も高まります。
(6)マインドフルネス(瞑想)
今に意識を集中することで「心配ごと」を忘れる習慣をつけましょう。
ぜひ、今日からお試しください。
次回は、「もっと伝わる!感情表現スキル」をお伝えします。