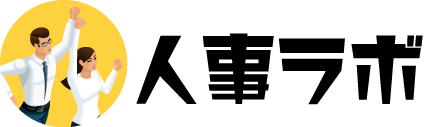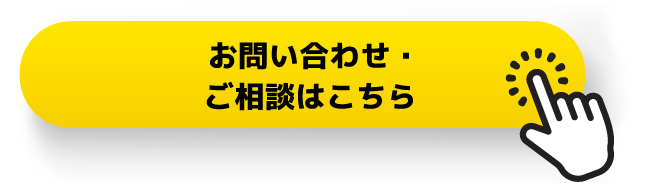物流業界の2024年問題~その2

女性トラックドライバーのSNSが人気を博してドラマ化が決定するなど、昨今スポットライトを浴びている「物流業界」。
エッセンシャルワーカーとして社会基盤を支えていながら、【2024年問題】という壁に直面しようとしていることは、第1回目のコラムにてお話ししました。
今回はその第2回目として、この問題から見えてくる課題について考えていきたいと思います。
目次
1、1つ目:労働時間の減少
法改定の適用に伴い、物流業界だけでなく建設・医療業界等でもさまざまな影響が懸念されている【2024年問題】。これらが具体的にどのような問題に繋がるのか。改めて考えてみたいと思います。
1つ目に思いつくのは、労働時間の減少。これは業界全体に大きく影響する懸念点です。
扱う商品やその積荷・荷下ろしにかかる時間等にもよりますが、これまでと比較して来年4月1日以降は約2割の労働時間が減少すると言われています。
距離で表現するのであれば、1日650km走っていた長距離トラックが520kmしか走れなくなる計算に。つまり今後は、既存エリアへの商品の輸送が難しくなり、取り引き先にも影響することが予測できます。
2、2つ目:深刻なドライバー不足
2024年問題が話題になるよりも前に生じている課題ではありますが、2つ目に挙げられるのは、業界全体でのドライバー不足です。
この問題は2024年4月以降、さらに深刻化する恐れがあります。
2023年に広報された有効求人倍率の全国平均が1.09に対して、業界を自動車運転従事者に絞ると2.43というデータが出ています(厚生労働省有効求人倍率データより)。
この仕事はデスクワークよりも身体を動かすほうが向いている方、運転免許等の資格を活かして働きたい方にとっては働きやすい業種と言えますが、それよりも拘束時間の長さ等が目立ってしまっており、仕事の魅力が伝わりづらくなっていることも影響しています。
業界・企業側が改善・変化に向けて取り組む必要がある課題と言えます。

3、3つ目:企業の利益への大きな影響
1つ目の労働時間の減少、2つ目のドライバー不足を採用という側面から考えると、今後は下記のような必要経費がかさんでくると予測されます。
【1】人件費:労働時間の減少による複合シフトや人員の増員にかかる費用
【2】採用費:新しくドライバーを採用するにあたっての費用
【3】設備投資費:業務の効率化を図るための新システムや設備導入にかかる費用
物流・配送の側面から見れば、日本の運送会社の99%が中小企業という現状があります。そしてその事業規模もさまざま。当然、経費の上昇はその経営を圧迫してくるでしょう。
またスタッフも複数のタスクを兼任している可能性が高いため、すぐに新しいシステムを適用できたり、スムーズに業務を引き継げるかは疑問が残ります。
また経費の上昇により、これまでの体制が維持できなくなる企業も出てくる可能性があるため、正社員採用をやめて業務委託の雇用を増やす等のさまざまな対策をする企業がこれからどんどん増えていくことが考えられます。
4、次回のご案内
日本経済を支え、今の時代に無くてはならない経済の動脈とも言える物流業界であるからこそ、人員確保の道を拓くことが、2024年問題への対策の一歩になると考えられます。
また流通基盤としてだけでなく、エッセンシャルワーカーとしてインフラを支える労働力の確保こそが、国民の暮らしの水準を守ることに繋がるという重要性においても、このタイミングで改めて考えていくことが大切でしょう。
当社では長年、物流業界の採用に関わってきたノウハウがございますので、こうした課題への対応についてぜひお気軽にお問合せいただけますと幸いです。
次回はさらにこの問題が与える世の中への影響を掘り下げながら、採用への課題解決に向けて別視点から切り込んでいきます。どうぞご期待ください。