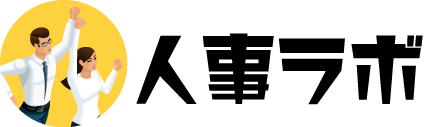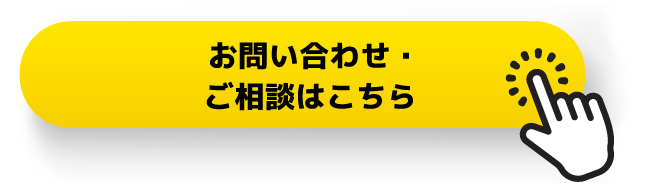ジョブ型雇用って何?近年注目を集めるジョブ型雇用を解説!
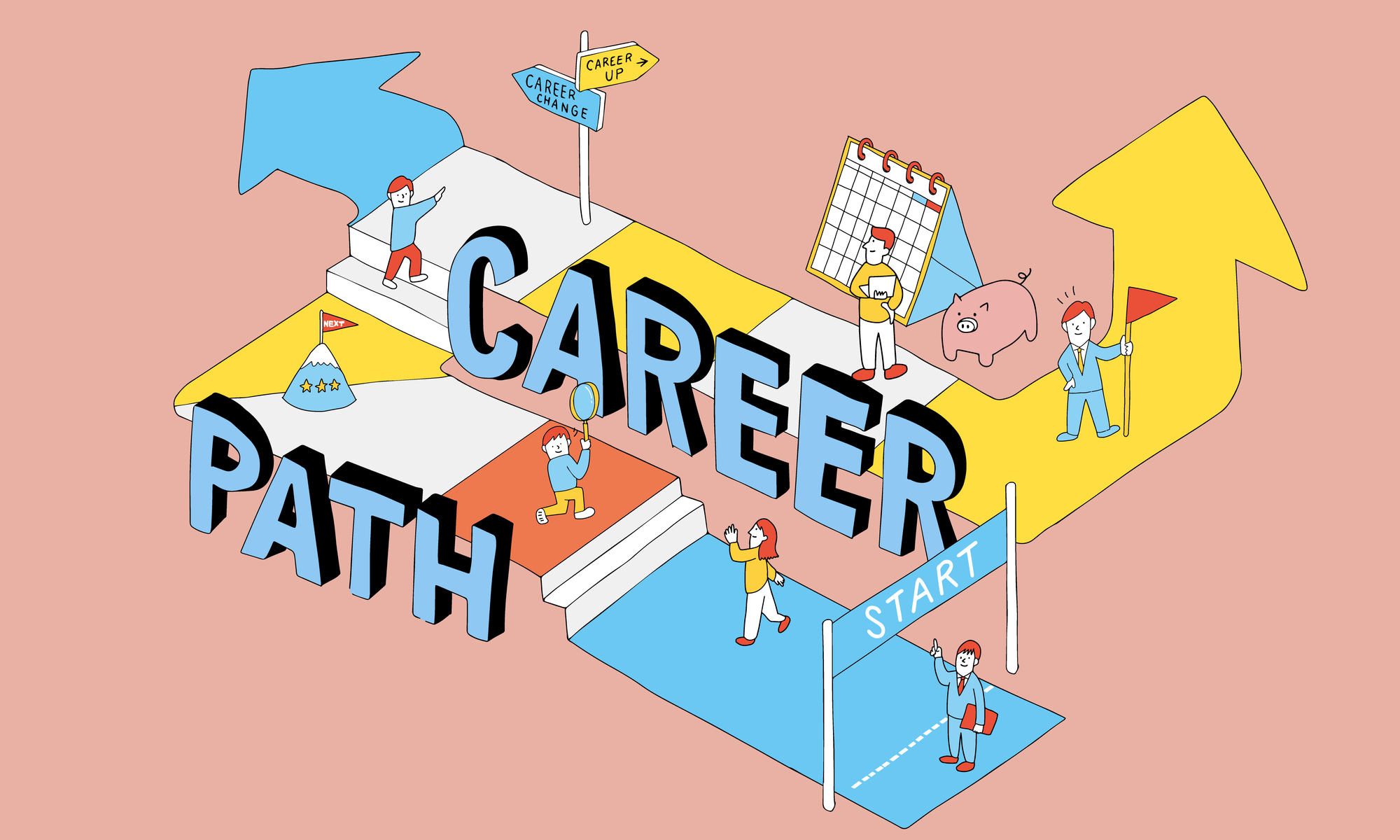
ジョブ型雇用って何?近年注目を集めるジョブ型雇用を解説!
近年注目を集めている「ジョブ型雇用」。
働き方改革やアフターコロナの働き方の文脈で、このキーワードを聞くことも多くなってきました。
でも、いざ「ジョブ型雇用」を説明するとなると、きちんと回答できる方は少ないかもしれません。
実際のところ、ジョブ型雇用は、個人・企業によって解釈や捉え方は様々で、
明確に定義づけるのは難しくもあります。
そこで今回は、ジョブ型雇用とは何なのか、
ジョブ型雇用を導入するメリットやその導入方法について詳しく解説していきたいと思います。
目次
-
ジョブ型雇用とは?従来型雇用との違いは?
-
働き手から見たジョブ型雇用のメリット・デメリット
- 企業がジョブ型雇用を導入するために必要なこと
1、ジョブ型雇用とは?従来型雇用との違いは?
・ジョブ型雇用とは?
「ジョブ型雇用」とは、企業が人材を採用する際に、職務内容(ジョブ)を明確に定義し、
その職務に最適なスキルや経験を持つ人材を採用する雇用形態のことです。
これまでの日本では「メンバーシップ型雇用」と呼ばれる従来型の雇用形態が主流でした。
ですが、これまでの終身雇用や年功序列といった雇用スタイルが崩壊しつつある現在の日本社会では、
従来のメンバーシップ型雇用を維持していくのは難しく、少しずつジョブ型雇用へシフトしていくべきなのではという声も出てきています。
・メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違いは?
では、簡単にメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用は具体的にどう違うのでしょうか?
それぞの特徴を簡単に表にまとめてみました!

比較してみると、会社(組織)をベースとするか、職務(個人)をベースにするかという違いが大きくあります。
メンバーシップ型雇用だと、雇用が守られる安心・安定性はあるものの、
あくまで長期雇用(長期の人材育成)がベースとなっているため、評価(役職や給与)が上がりにくいケースや、
キャリアが個人の志向性と合わないケースが発生する可能性が高くなります。
一方、ジョブ型雇用だと、雇用が不安定になりますが、業務範囲や評価が明確で、より個人の志向性も反映しやすい傾向にあります。
2、働き手から見たジョブ型雇用のメリット・デメリット
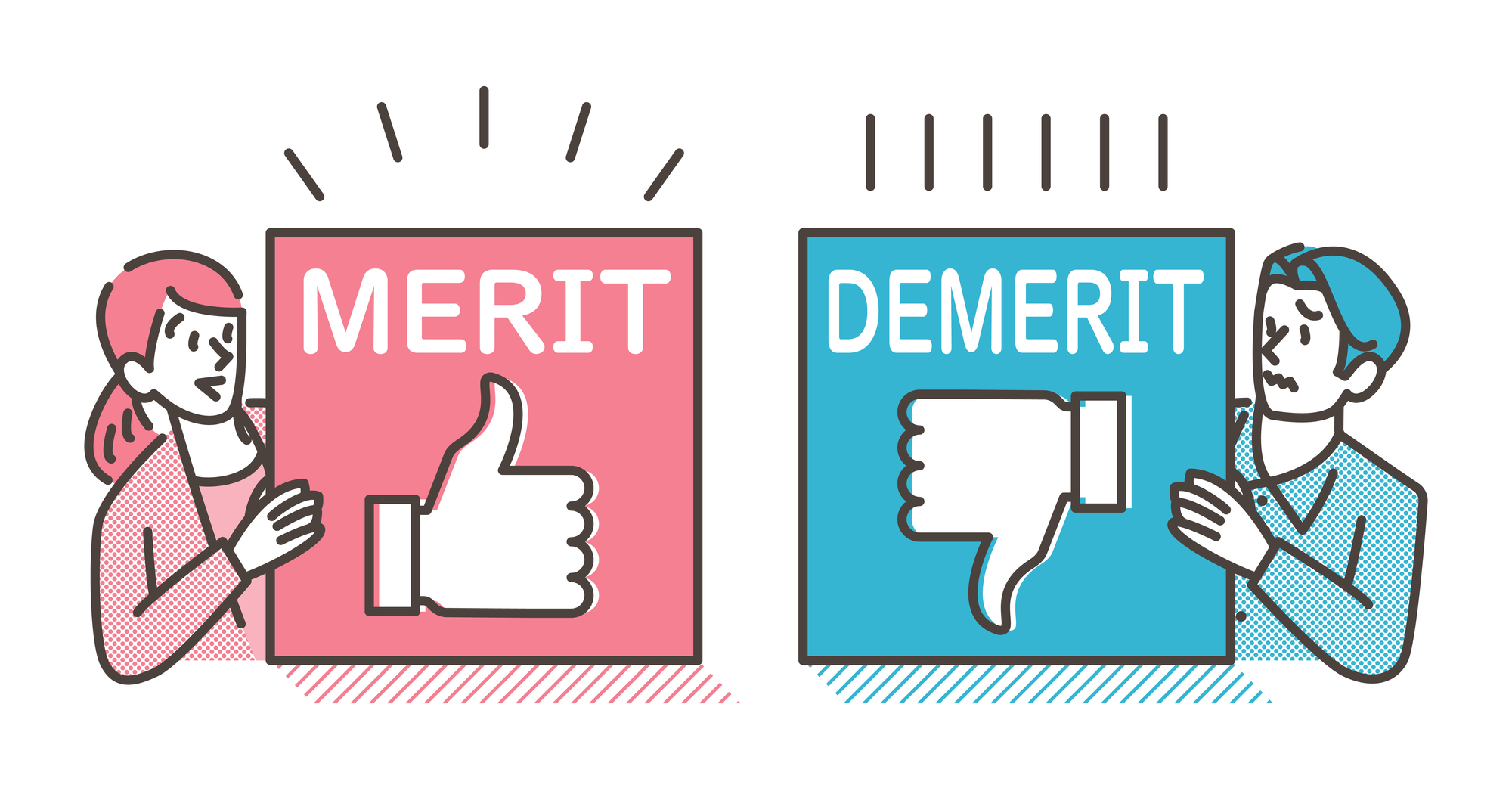
ジョブ型雇用は、企業だけでなく、働き手となる個人にも大きな影響を与える雇用システムです。
そこで、働き手から見たジョブ型雇用のメリット・デメリットを整理していきましょう。
【働き手から見たジョブ型雇用のメリット】
- 個人のスキルが活かせる
職務をベースとしてキャリアを積んでいけるため、専門性をより深めることができます。
会社都合で別のポジションに異動になったり、領域外の仕事を兼務させられることもないので、
自分の得意な分野や興味のある仕事に集中することができます。
- 評価が明確
成果が報酬に直結するため、自分の成果が正当に評価され、給与や昇進に反映されやすいという特徴があります。
職務内容が明確化されているため、客観的な評価を受けやすく、キャリアパスも明確になりやすいです。
- 働き方の自由度が高い
組織体制よりも職務遂行が優先されるため、リモートワークやフレックスタイム制など働き方の自由度が高まる傾向があります。
雇用形態も正社員だけではなく、条件さえ合意できれば契約社員やアルバイトなど様々な働き方を選択できる柔軟性もあります。
【働き手から見たジョブ型雇用のデメリット】
- 雇用の不安定性さ
契約社員の場合、契約期間が短い場合があり、雇用の不安定さを感じる場合もあります。
また、企業の業績が悪化した場合、メンバーシップ型雇用よりもリストラに遭いやすい可能性が高まります。
- 自己責任の部分が多い
メンバーシップ型雇用では会社が主導して人材育成を行ってきましたが、ジョブ型雇用になるとスキルアップの責任は自分自身にあります。
キャリアップするためには、常に新しいスキルを身につけることが求められ、自己投資が不可欠となります。
- 人間関係の希薄化
メンバーシップ型雇用と比較して、チームワークを重視する企業・個人が少ない可能性があります。
組織としての一体感よりは、プロフェッショナルとしてのスキルが求められるため、人間関係が希薄になる可能性もあります。
働き手からすると個々のスキルを活かしたり働き方の自由度が高くなる、という面がメリットかと思いますが、
半面、 雇用の安定面や人間関係が希薄になる、という面がデメリットになりそうです。
3、企業がジョブ型雇用を導入するために必要なこと
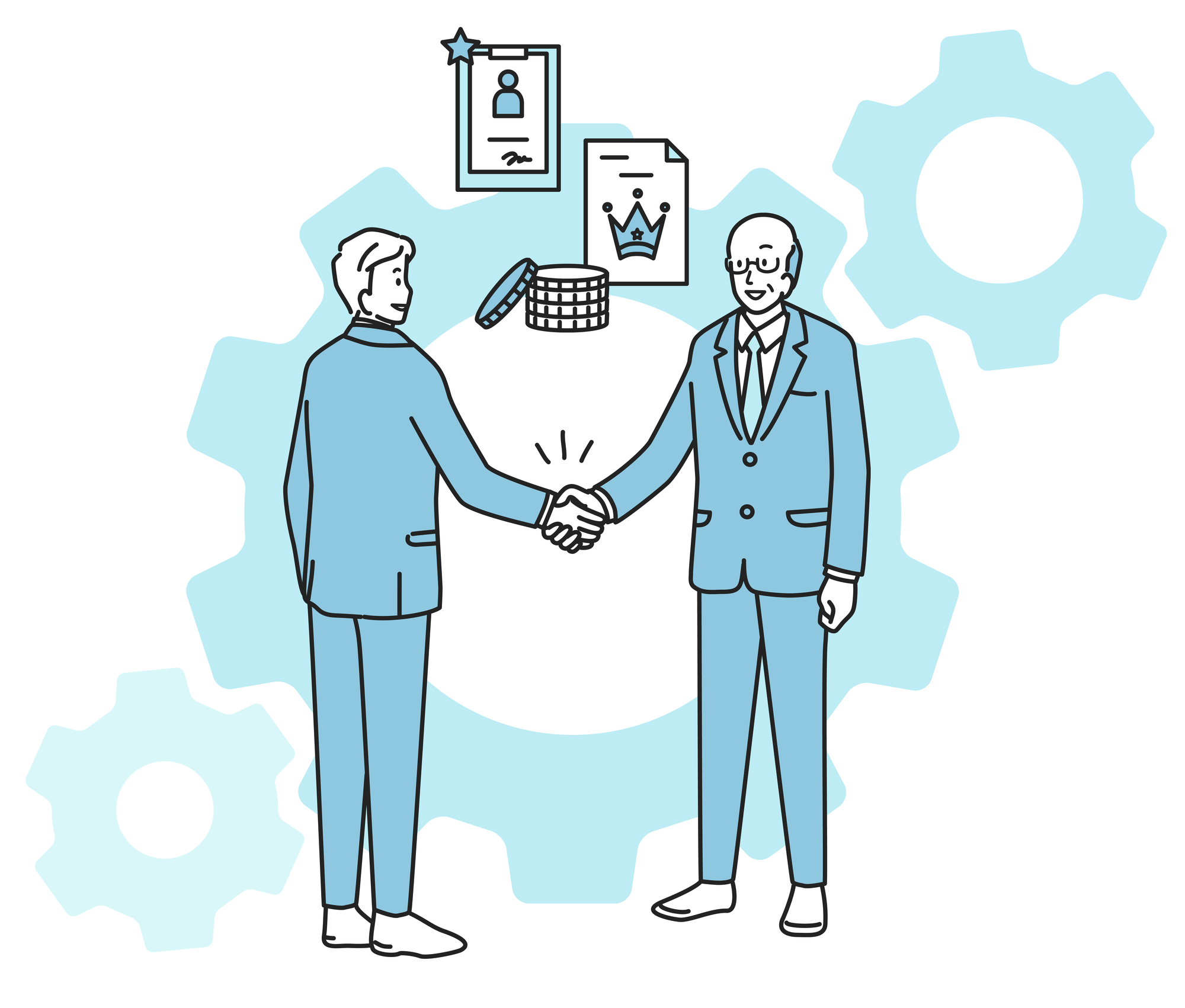
これからの日本社会を考えていくと、ジョブ型雇用への移行は必然なことかもしれません。
でも、メンバーシップ型雇用だった企業が、今すぐジョブ型雇用に切り替えるのは正直難しいと思います。
そのため、メンバーシップ型雇用の中に一部「ジョブ型雇用の施策」を導入する企業が増えています。
今回は、メンバーシップ型雇用から段階的にジョブ型雇用シフトするために
必要なことについてまとめてみました。
・ジョブ(職務)の定義・領域を明確にする
メンバーシップ型雇用の企業では、職種が決まっているものの業務範囲があいまいなことも多くあります。
あれもこれも何でもやっているオールマイティな方もいれば、
同じ職種なのに限定的な業務しかできない方もいます。
まずは、ジョブの定義・領域を決めて、
そのジョブに必要なスキル・経験・責任範囲などを整理していくことが肝心です。
これを行うことで、個人の評価が明確になり、採用の方針も分かりやすくなるでしょう。
・職種別採用・社内公募を導入する
ジョブの定義が明確化すると、その基準にもとづき職種別採用やキャリアパスの枠組みをつくりやすくなり、
ジョブ型雇用への移行がより進行しやすくなります。
採用も総合職として新卒で年に一回一括採用するのではなく、
職種別にピンポイントの人材を狙っていくスタイルに変化していきます。
異動に関しても、会社からの一方的なものではなく、
本人の同意や意志を尊重した「社内公募制度」を設けることが大切です。
・職務別・スキル別教育体制を構築する
メンバーシップ型雇用では同期一括で同じ研修・教育を受けるケースが多くありました。
しかし、ジョブ型雇用に移行すると、職務別・スキル別の研修・教育を行う必要が出てきます。
個人によって差が出てくるので、自発的にプログラムを選択できるeラーニングなども効果的です。
ただ、個人によってモチベーション差が生まれてしまうのも事実としてあります。
メンバーシップ型雇用に慣れてしまっている方には、
自律的なキャリア形成やスキルアップを促すようなサポートも必要になってくるかもしれません。
★採用のご相談は飛竜企画へ★
いかがだったでしょうか。ジョブ型雇用が注目されているものの、
これまでのメンバーシップ型雇用から切り替えるのには、
もう少し時間と労力がかかりそうです。
とはいえ、未来の日本社会の展望を考えていくと、
今後ジョブ型雇用にフィットした採用方法や働き方のスタイルが増えていくと予想されます。
飛竜企画では、「ジョブ型雇用」に対応した人材採用のご相談から、
アルバイト・中途・新卒採用まで採用に関する幅広い課題に対応しています。
何かご相談があれば、ぜひお気軽に飛竜企画までご連絡ください。
※参考文献:今さら聞けない「ジョブ型」雇用