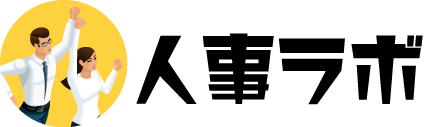2025年度卒学生向けインターンシップはどう変わる?~インターンシップ「4タイプ」の解説と活用~

今回は<タイプ1><タイプ2><タイプ4>についてまとめました。
前回のブログでは、インターンシップの定義が変わるということで、その経緯と、新たに分類・整理されたインターンシップの4つのタイプの概要、そして、インターンシップ期に獲得した学生情報を採用活動に使用できる<タイプ3>について説明しました。
→前回ブログ「2025年度卒学生向けインターンシップはどう変わる?」
今回は残り3つのタイプについてご説明します。
1、前回のおさらい
- インターンシップと新卒採用の現状をふまえ、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の三省が合意のもと、定義変更がなされました。
- インターンシップは内容や目的によって、産学協議会によって4つのタイプに分類されました。
- 2025卒採用より、<タイプ3>のインターンシップで取得した学生情報を、採用活動開始以降、使用することが可能になりました。
■4つのタイプ概要
| タイプ | 内容 | 目的 | 取得学生情報の 採用活動への活用 |
|---|---|---|---|
| <タイプ1> | オープン・カンパニー | ■個社・業界の情報提供・PR | NG |
| <タイプ2> | キャリア教育 | ■教育 | NG |
| <タイプ3> | 汎用的能力・専門活用型 インターンシップ |
■就業体験 ■自らの能力の見極め ■評価材料の取得 |
採用活動開始 以降に限り可 |
| <タイプ4> | 高度専門型 インターンシップ |
■就業体験 ■実践の向上 ■評価材料の取得 |
▲(試行中) |
出展:採用と大学教育の未来に関する産学協議会2021年報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」
このうち、2023年2月までに取得した学生情報の採用活動への活用は、<タイプ3>の場合のみ「採用活動開始以降に限り」利用できるとしました。高度専門型の<タイプ4>は修士向け、博士向けのプログラムを現在産学連携により試行中のため、一旦「▲」としています。
また、「採用活動開始以降」とは具体的に、2023年3月以降の広報活動、2023年6月以降の採用選考活動を指します。
2、<タイプ1>オープン・カンパニーとは?
大学が行う「オープン・キャンパス」の企業版・業界版・仕事版です。
| プログラムイメージ | 主に、企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが 主催するイベント・説明会を想定。 |
|---|---|
| 就業体験の有無 | なし |
| 実施時期 | 時間帯やオンラインの活用など学業両立に配慮し、 学士、修士、博士課程の全期間(年次不問)。超短期(短日) |
| 学生情報の 採用活動への活用 |
不可 |
3、<タイプ2>キャリア教育とは?
教育的・社会貢献的側面が強く、企業だけでなく大学による実施を想定しています。
| プログラムイメージ | 主に、企業がCSRとして実施するプログラムや、 大学が主催する授業・産学協働プログラム。 |
|---|---|
| 就業体験の有無 | 任意 |
| 実施時期 | 学士、修士、博士課程の全期間(年次不問)。 企業が行う場合は時間帯やオンライン活用など学業両立に配慮。 |
| 学生情報の 採用活動への活用 |
不可 |
4、<タイプ4>高度専門型インターンシップとは?
産学が連携して行う、研究職などを対象にした高度でかつ専門性の高いプログラムです。
| プログラムイメージ | 該当する「ジョブ型研究インターンシップ(文科省・経団連が協働で試行中)」「高度な専門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(2022年度に更に検討)」は、大学と企業が連携して実施するプログラム。 |
|---|---|
| 就業体験の有無 | 必ず行う |
| 実施時期 | ー |
| 学生情報の 採用活動への活用 |
※試行中 (産学協議会の2021年報告書としては、採用活動開始以降に限り可) |
5、注意したい留意点
- <タイプ1~4>はどれもキャリア形成支援の取り組みであって採用活動ではないため、学生は改めて採用選考のためのエントリーが必要。
- <タイプ1~4>からなる学生のキャリア形成支援は、産学が協働しながらそれぞれを推進していくことが重要。
- 今回、政府が定める現行の「就職日程ルール」を前提に検討。
- インターンシップ<タイプ3、4>に参加できる学生は、就活予定者の一部学生への周知が重要(入社就職先でのインターンシップ参加経験がなくても、採用選考へのエントリーは可能なことへの周知)。
- <タイプ3>は、産学協議会が定める基準を満たす場合に「産学協議会基準に準拠したインターンシップ」と称することができる(準拠マークを付すことが可能)。
- 各タイプの活動を通じて取得した学生情報を採用活動に活用することについて「タイプ1、2は活用不可」「タイプ3、4は採用活動開始以降に限り活用可」。 ※但しタイプ4は現在試行中
6、選択肢が増えたインターンシップ
タイプ1や2は、従来1dayもしくは2dayで実施されていたような、近年多く企業が実施しているインターン
シップに分類されます。実施期間や職業体験についても必須ではないため、いろいろな組み合わせのバリエーションで企業自体の魅力や該当企業の仕事への興味がわくようなプログラムが出てくることが想定されます。
一方、タイプ3や4は、実施期間が長い分、現実的に実施ができる企業が限定されてしまいかねないことが懸
念されましたが、性質や特徴を類型化したことで双方に選択肢が広がったように思えます。
以前から感じていたことですが、全ての学生が一斉に就業感が形成されるものではないはずで、多様性という意味でも、個々人の就業感の醸成具合に合わせてインターンシップが実施され、学生が選択できるという意味でも良い第一歩なのではないかと思われます。
2024卒採用でも、この方針をふまえた動きが出てくることが予想されます。今後もインターンシップについては様々な議論や施策が出てくると思いますので、このブログでお伝えしていきたいと思います。