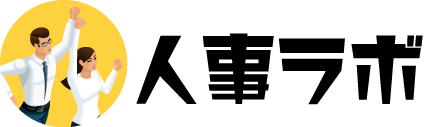クリティカル・シンキング(批判的思考力)~心理学をビジネスに活かそう(26)

「あなたが上司だったら、どんな部下がいてくれたら、ありがたいですか?」
「良い部下とは」その問いに答えるキーワードの一つが「批判的思考力=クリティカル・シンキング」です。決して否定的な意味合いでの批判ではありません。上司からの指示や与えられた役割を問い直し、自分の見解を主張する力のことを指します。
■貢献力×批判力=協働者(良い部下)
●「貢献力」を発揮する部下

上司の指示や与えられた役割を受け入れて、献身的に考え行動してくれる「貢献力」を発揮する。これは、どんな上司でも喜ばしい部下ですね。
●「批判力(批判的思考)」を発揮する部下
もう一つ、部下に発揮して欲しいのが、「批判力(批判的思考)」です。「クリティカル・シンキング」と言う言葉で定着していますね。
一見、「批判力」というと、否定的な印象を受けやすい言葉に感じます。上司の指示や考えを批判するとなると、関係が悪化する気がしてしまいます。
しかし、上司は万能ではありません。
上司だって、間違えることもあれば、考えが足りないこともあります。
慣例や過去の成功体験に引きずられて、同じやり方しか思いつかないこともあります。
むしろ、若手の方が、今風の新しいやり方を知っていることもあるでしょう。 
つまり、上司の指示や与えられた役割を受け入れて、献身的に考え行動してくれる「貢献力」を発揮しつつも、「上司からの指示や与えられた役割を問い直し、自分の見解を主張する」=「批判力」も発揮する部下こそ、あなたのチームにとって、とてもありがたい存在となるのではないでしょうか。
■クリティカル・シンキング(批判的思考力)とは
辞書には『物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角度から検討し、論理的・客観的に理解すること(goo辞書より引用)』とあります。
「本当にそうか」
「その考え(論理)を支える事実はあるか」
「矛盾する事実はないか」
「情報源はどこか、適切か」
これらを問いかけながら、経験や直観だけに頼らず、問題の本質に到達するための思考法です。
■クリティカル・シンキングを発揮するための思考習慣
(1) 事実と意見(解釈)を区別する
●何が「事実」で、何がその人の「意見(考え・解釈)」かを混同しないこと。
・「彼は今週月曜日に欠勤した」(事実)
・「彼は休み明けの月曜日から欠勤するような人」(事実+解釈)
●特に「程度言葉」には注意しましょう。
・「ちゃんと」「しっかり」「少ない」「多い」「全部」「ほとんど」「みんな」「誰でも」・・・
●情報源は妥当か
・ 社員に聞いてみたところ・・・
・ ニュースで見たんだけど・・・
(2) 先入観に流されていないかチェックする
・ 彼には経験が無いし、成功するはずがない
・ 当社は大手じゃないんだから、できるわけがない
・ 世の中、そんなうまい話しがあるはずがない
(3) 前提条件が正しいか確かめる
・ 繁忙期は避けるべき
・ スピードアップのためには増員すべき
(4) 多角的・客観的に考える
・ 営業担当の満足度はどうか
・ お客様の納得度はどうか
・ 経営者の満足度はどうか
・ 製造部の理解・協力はどうか
・ 競合会社の視点からはどうか
・ 市場の視点からはどうか
・ 短期的な成果としてどうか
・ 中長期的視点からみてどうか
・ 成功確率からみてどうか
・ 社員のモチベーションからみてどうか
■日頃から意識してみましょう
ビジネスの会話で
上司からの指示を受ける時
会議やミーティングで
仕事の計画を立てる時
提案書・企画書を作成する時
日常業務でも意識することで鍛えられそうですね。